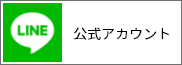8月2日、DOR150号記念公開シンポジウムが開催されました。本号では、駒澤大学経済学部現代応用経済学科准教授・大前智文氏の報告要旨を紹介します。
岐阜県の産業
岐阜県は全国的にも製造業を中心とした社会・経済・産業構造を形成し、愛知を中心とした中部地域のモノづくりの一翼(外縁部)を担っています。その製造業は輸送用機械と一般機械の2本柱が支えるとともに、良質な天然資源と多種多様な技術・技能に由来する、家具・木工、刃物、紙、陶磁器、アパレルなどの伝統産業・地場産業も盛んです。
岐阜同友会の景況アンケートの特徴
岐阜同友会においても製造業を営む会員の割合が大きく、第一義的な重要性を有しています。また、「社長の学校」として、「志ある」あるいは「よく学ぶ」と表現されるような中小企業経営者の集まりである岐阜同友会の基本属性を前提として、その分析を進めています。
岐阜同友会の景況アンケート調査について、送信数は約700社、返信数が約150社、回答率が約20%を安定して得ています。これは当該地域における各自治体や行政機関、金融機関などの実施する調査と比較しても遜色のない、岐阜県下最大規模の中小企業の景気実態に関するアンケート調査となっています。
近年の景況の推移
業況判断DI値と業況見通しDI値の推移を見ると、2018年10月の国内の景気が拡大局面から後退局面に転換する「景気の山」、2019年10月の消費税率の引き上げ、2020年3月からのコロナ禍、2022年3月からのロシアによるウクライナ侵攻などの影響を反映しており、その調査の妥当性・適切さが表れています。そのうえで2023年9月ごろから業況判断、業況見通しともにマイナス圏に位置しており、「悪い業況見通し」の通りに「悪い業況判断」が実現する傾向が見られます。これはアンケート回答者のマインドの悪化も表していることが推測されます。(図1)
売上高(前年比)DI値と経常利益DI値の推移を見ると、これまでずっと連動してほぼ平行に推移してきた両指数が、2022年12月ごろからバラバラに動くようになりました。これは物価・コスト上昇分の価格転嫁の動きを表しています。物価・コスト上昇は継続しており、価格転嫁も進められているようですが、そのたびに売上高(前年比)DI値は落ち込んでいく(買い控えられる)ため、経営的には厳しい状況が続いています。
このために会員企業には当該地域一帯に広がるトヨタ的な「よりよく、より安く」という価値観や経営姿勢に対する疑問が生じつつあることに加え、日本経済・産業の地位や構造の変化に伴う岐阜県経済・産業の構造の変化を現実のものとして認識・実感しつつあります。
また業種別、地域別、総従業員数別(企業規模別)に分析を進めると、景気後退基調とともに進む社会・経済・産業構造の変化に対応できているかできていないかの二極分化、換言すれば、「よい傾向」と「悪い傾向」の二極分化が進行しています。そして、地域のリーディング産業である製造業の危機的状況(図2)、岐阜県内の地域的格差の顕在化・表面化、政策対象として見過ごされがちな総従業員数10~29名のような規模の中小企業の窮状などが新たな課題として見いだされます。
「中小企業家しんぶん」 2024年 10月 5日号より