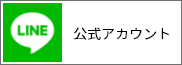中同協は、2022年10月に『企業変革支援プログラムVer.2』を発刊しました。今回は、福田圭祐・島根同友会経営労働委員長の活用事例を紹介します。
島根同友会での活用
島根同友会・経営労働委員会では、『企業変革支援プログラムVer.2』を会内に広め活用するにあたり、段階を経て時間をかけて取り組むことにしました。
まずは、何のためにこのプログラムを使うのか、そして、どう活用するのかを学ぶため、4月に中同協経営労働副委員長/徳島同友会副代表理事の吉武恭介氏をお呼びし、企業変革支援プログラムに関する体験報告をしていただきました。参加できなかった人には、アーカイブ配信を行いました。
体現者の方に報告してもらうことで、実際の活用の仕方・考え方が理解でき、分かりやすかったという会員からの声を聞きました。
5月からは、振り返りで企業変革支援プログラムVer.2勉強会を行っています。吉武氏の報告のアーカイブを1時間視聴し、使い方をセミナー形式で学んでいます。視聴した会員からは、「何度も同じ動画を見ているのだが、毎回感じるポイントが違う」と言われます。どういうところでそれを感じるかは、その会員さんのその時の経営課題によるものであると思いますが、Ver.2は、どのカテゴリーと項目がその人の解決したい課題であるかを認識できるプログラムだと思います。勉強会では、エントリーシートを1つ1つ読み上げ、直感で12ページ(エントリー自己診断)のコピーに記入してもらいながら、パソコンが手元にある人は、直接e.doyuにも登録してもらうようにしています。
経営労働委員会主催の勉強会は、3~6名くらいの参加です。少人数で行うことで、理解度が上がっていると思います。参加者が、各支部・部会・委員会にて中心的に企業変革支援プログラムについて伝えていくようにしてもらっています。実際に支部幹事会で企業変革支援プログラム勉強会を取り入れた際には、その場で10名の理解者が生まれました。今後も、各支部・部会・委員会や、支部例会にて経営体験報告と企業変革支援プログラムを合わせることにより広めていく計画です。
社内での活用
(株)KUTOでは、「Ⅳ市場・顧客及び自社の理解と対応」の中で、病気や障害で着替えに不自由を感じる人を幸せにするシャツ【スルースリーブ】の事業化において市場・顧客の変化やニーズを正しく把握しているのかなど、進めている事業と企業変革支援プログラムを重ね合わせて検証しながら社会的な課題解決に向けて取り組んでいます。
また、社内での活用としては、社員がエントリーシートの項目の中で、自社に当てはまると思う10項目をピックアップし、社員にどういうことかをわかりやすく説明した上で、経営者と会社の評価を社員が行うのに使っていきます。
経営者自身が成熟度のレベルを確認するとともに、社員から見た経営者・会社のレベルを確認することで、毎年の経営指針の更新に取り入れていきます。
島根同友会経営労働委員長 (株)KUTO代表取締役 福田圭祐
「中小企業家しんぶん」 2024年 12月 5日号より