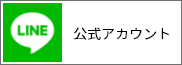中小企業を取り巻く環境と課題
近年のわが国では、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など自然災害が頻発しています。また、新型コロナ感染症の世界的パンデミック、ロシアによるウクライナ侵攻といった国際的な危機が中小企業経営に大きな試練を与えています。他方、消費増税に伴う電子帳簿保存法によるインボイス制度の導入、加速度的に進んでいる少子高齢化による労働力不足、働き方改革は中小企業が乗り越えなければならない試練です。
現在、中小企業には課題が多く存在していますが、経済産業省・中小企業庁や厚生労働省は、政策対応として、新政策を毎年のように実施しています。
支援策の活用状況
2024年第34半期のDORオプション調査では、コロナ感染症がひとまず収束した2023年度以降における補助金、助成金などを中心とした施策の活用状況に関するアンケートを実施しました。有効回答数は1072件でした。
まず、「利用している支援策」に関しては、複数回答で「活用していない」が39%で最も多いものの、残りの約6割の企業が何らかの補助金、助成金などを活用しているといった結果になっています。
「利用している支援策」の内容は、多い順に「政府系金融機関の融資制度」24%、「IT導入補助金」22%、「事業再構築補助金」10%、「ものづくり・商業・サービス補助金」9%と経済産業省の補助金などが上位を占めています。これらの補助金は、業種別に見るとサービス業での活用割合が低くなっており、今後の課題となります(図1)。

「事業再構築補助金」は申請するための書類作成のハードルが高いですが、同時にその支援は金額的に手厚いものとなっています。DOR回答企業がそうした支援に挑戦し、活用している企業の回答が105件、約1割も存在することは、優れた経営計画を策定する能力が高い企業が層として存在していることを示しています。
とはいえ、事業再構築補助金を採択した企業からは、補助金交付を感謝しつつも「事業完了後の審査に時間がかかっており、事務負担と資金計画に支障」(福岡、製造業)、「報告書提出の期限が短い、使い勝手が難しい」(奈良、流通・商業)、「実績報告がなかなか通らず、何度も手戻り」(愛知、製造業)との声もあります。今後は同友会の例会などで、補助金獲得から成果報告書作成までの過程に関して、PDCAサイクルを踏まえた学習会を開催し、具体的な活用を後押ししていくことも効果的だと思われます。
その他の経済産業省の補助金は、「小規模事業者持続化補助金」4%、「中小企業省力化投資補助金」3%と低い割合となっています。「小規模事業者持続化補助金」については、その対象が小規模企業のみなので、同友会企業でその対象となる企業がそもそも少ないことが理由と考えられます。また、「中小企業省力化投資補助金」は、人手が不足している中小企業がその不足を補うための省力化機器を購入する際の補助金です。2024年度の新施策であるため、まだ認知されていないことからこのような数値となったことが考えられます。
他方、厚生労働省の助成金については、「人材開発支援助成金」6%、「雇用調整助成金」5%、「働き方改革推進支援助成金」3%、「人材確保等支援助成金」2%とその活用割合は低い傾向になっています。人手不足が顕著である今日、失業対策で活用される「雇用調整助成金」の活用状況が低いことは、理解できます。人材育成、働き方改革、テレワークの推進、外国人活用といった今日的な課題のために「人材開発支援助成金」、「働き方改革推進支援助成金」、「人材確保等支援助成金」が用意されています。これら助成金の活用状況が低いことは政策内容がニーズに適していないことが考えられます。実際、「1名抜けただけでも業務が回らなくなりいくら金銭の補助があっても役に立ちません」(愛知、サービス業)との声が熟練工に依存しているトラック整備の企業からあります。政策を企画立案する場合、実際の現場をよく考慮する必要があります。
経済産業省の補助金には採択率があり、申請すれば全て支給されるものではありません。それとは反対に厚生労働省の助成金は、要件に合っていれば、支給されます。今日の人手不足は深刻です。同友会企業が厚生労働省の助成金を申請することは、今後重要となってくると考えられます。
支援策を活用しない理由
次に、「活用していない理由」については、複数回答で「自社が必要とする支援がない」35%、「支援を受ける必要がない」30%、「支援内容をよく知らない」22%が上位となっています(図2)。「自社が必要とする支援がない」とするものは、サービス業での割合が高く、「支援を受ける必要がない」とするものは、製造業での割合が低いという数値になっています。これは、サービス業に対する支援施策が少なく、製造業における施策が多いことの反映です。「支援内容をよく知らない」とするものが2割以上も存在していることは、同友会において施策普及の仕組みを考えることが今後の課題となります。

実際、「情報までたどり着けない」(北海道、流通・商業)、「国や自治体等でもっと大々的に宣伝してほしい」(埼玉、建設業)、「同友会で支援策を活用、実践している報告を積極的に行ってほしい」との声は重要です。
また、「電子申請が困難」としたものが1%であることは、事業者が行政サービスを受ける際に登録するGビスIDが普及していることの反映であると解釈できます。
支援策情報の入手経路
最後に、「支援策関連情報の入手先」については、複数回答で「金融機関」38%、「同友会」37%、「商工会議所・商工会」37%が上位を占めています(図3)。同友会企業にとって、これら機関は、日常の企業経営において、日々接する機関です。特に同友会では、例会活動時などを通じて、支援施策関連情報の共有化のいっそうの推進が、今後の課題となることは、言うまでもありません。

また、「税理士」17%、「社会保険労務士」12%と士業からの情報経路がそれほど多くないのは、現状において士業は行政に提出する書類作成がメインであり、コンサルタント業務までは対応していないことが考えられます。同友会において、士業の会員企業も多く存在しています。彼らが施策情報を意識しながらこれからの業務を展開することは、今後の課題となると考えられます。いずれにせよ、同友会は組織的に補助金、助成金の獲得のための体制をつくることが求められています。
「中小企業家しんぶん」 2024年 12月 15日号より