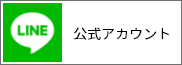中小企業政策の流れについて学ぶ機会がありました。
1963年の中小企業基本法の制定から、1999年の改正を経て現行の法律となっています。この間、2014年には小規模企業振興基本法が制定され、卸売業・小売業・サービス業は5人以下、他の業種は20人以下の中小企業が「小規模企業」と定義されました。2024年に改正した産業競争力強化法では、常時雇用している従業員数が2000名以下の企業を「中堅企業」と定義し、新しい支援策を実施することになりました。このように、「大企業」「中堅企業」「中小企業」「小規模企業」と企業規模ごとの類型ができ、その類型に沿った中小企業政策が展開されてきています。
そこで、国は今後の中小企業政策の方向性をどう考えているのでしょうか。2024年9月2日に中小企業庁は「今後の中小企業経営への提言及び中小企業政策の方向性」を発表しています。同友会では同友会運動の新しいステージに向けた議論が始まっていますが、国のほうでも「中小企業・小規模事業者は雇用の約7割・付加価値額の約5割を占める、経済・社会の核心的存在であり、中小企業経営のあり方は、我が国経済がデフレ構造から脱却し、新しいステージに移行できるか否かを大きく左右する」とあり、日本経済の新しいステージおいての中小企業の重要性に触れています。
中身を見てみると、中小企業の「稼ぐ力」の強化を上げ、経営者の「自己変革力」が問われていること、そして「攻めの経営」が必要とあります。そのためには、経営者として「キョロキョロ」という表現で、アンテナを高くし、あちらこちらのネットワークに顔を出すことなどが重要だとあります。
企業類型ごとの施策では、(1)小規模事業者、(2)ローカルゼブラ企業、(3)スケールアップ(100億企業)を志向する中小企業と分けています。ローカルゼブラ企業とは、事業を通じて地域課題解決を図り、社会的インパクトを生み出しながら、収益を確保する企業。この新しい言葉の「ローカルゼブラ企業」にも注目しましたが、懸念したことは中小企業政策で「100億企業」を志向する中小企業の支援を打ち出しているところでした。本来であれば、1億円の企業を100社生み出すような政策が求められるのではないかと思います。
近年、中小企業の「生産性向上」や「新陳代謝」というワードが国の政策などに頻繁に使われています。「新陳代謝」からは「中小企業再編論」がイメージされ、生産性の低い中小企業は再編すべきだという印象を受けます。また、国の使用する「新陳代謝」には、廃業促進ということが裏にはあると研修で学びました。個々の自助努力を促し、企業内で成長を伴う企業変革をし、そういう意味での「新陳代謝」を促すことが重要ですが、近年の中小企業政策は、中堅企業やスケールアップ企業、スタートアップ企業などにシフトしていると懸念しています。「中小企業憲章」にある「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役である」の精神のもとで中小企業政策を進めることが重要ではないかとあらためて感じます。
(I)
「中小企業家しんぶん」 2024年 12月 15日号より