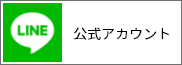2024年も終わろうとしています。コロナ禍から日常が戻り、久しぶりに忘年会を開催しているところもあるのではないでしょうか。飲食店にとっては繁忙期となっているかと思います。そのような中、2024年12月3日に(株)帝国データバンクが発表した「『居酒屋』の倒産動向(2024年1-11月)」によると、大衆酒場や焼き鳥店などの「居酒屋」が203件倒産(負債1000万円以上、法的整理)したことが明らかになりました。この数値は、コロナ禍の打撃を受けた2020年(189件)を大幅に上回っており、年間最多を更新することが確実となっているとのこと(図)。緊急事態宣言で休業要請が行われたコロナ禍よりも倒産件数が増えている現状から、業界の厳しさは一層深刻度を増していることが分かります。

倒産件数が増加している理由として、以下の点が挙げられています。収入面では、インバウンドによる消費は好材料ですが、大規模な宴会から少人数での飲み会にニーズがシフトしていることや物価高による節約志向の高まりで、来店頻度や客単価の低下の影響があるようです。お酒を飲まない若者も多くなっていますので、居酒屋自体に行く人が少なくなり、さらにノンアルコール飲料を選ぶケースが増加し、客単価も下がる傾向なのでしょう。
コスト面では、原材料高で仕入れ価格の高騰もしくは高止まりがあり、価格転嫁が満足にできていない状況もあります。人手不足問題も深刻な中、最賃上昇による就業調整の問題もあると思われます。当然人件費の上昇のほか、水道光熱費、地代家賃なども増加しており、収益を大きく圧迫しているのが飲食店の置かれている状況です。2024年度の居酒屋市場規模(事業者売上高ベース)は、推定で約1兆6,600億円とされています。コロナ禍の影響で大きく落ち込んだ21年度(約8,900億円)から年々増加傾向にあるものの、コロナ前の水準には達していません。価格が上がっているにもかかわらず、売り上げも回復しない状況は業界の深刻さを物語っています。実際に、2023年度における居酒屋の損益状況は、最終損益が「赤字」となった居酒屋が約4割を占め、コスト増による収益の圧迫で「減益」のケースを含めた「業績悪化」の割合は6割を超えています。
このままでは、地域で愛されてきた居酒屋が消えていくことが懸念されます。価格転嫁をしっかり行い、付加価値を向上させるための事業者の自助努力は必要だと思いますが、それも限界にきています。政府の減税政策、経済対策、物価対策、エネルギー対策など消費を活性化する政策が必要です。そして、収入の壁を引き上げ、もっと働ける・稼げる・消費できる政策の実現が望まれます。
「中小企業家しんぶん」 2024年 12月 25日号より