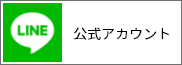11月14~15日に、第8回人を生かす経営全国交流会in長崎が開催されました。2日目に行われた実践報告の内容を紹介します。
一燈照隅、万燈照国
“誰もが活躍できる環境への架け橋”
飯田青果(有) 代表取締役 飯田 弘巳氏(長崎)
(長崎同友会理事・ダイバーシティ委員長)
飯田青果は、約60年前に祖父が創業しました。現在は法人化し、20名ほどのスタッフと共に、玉ねぎ、レタス、ジャガイモを中心とした青果物を取り扱っています。また、生産部門である「いいだ農園」は父が立ち上げた事業で、現在は私が経営を引き継ぎ、地域の農業基盤を支える役割を担っています。
地域農業の現状と課題
私たちが活動している長崎県南島原市では、多くの農家が品質の高い野菜や果物を生産しています。農業の現場は常に課題に直面しており、特に天候や市場の需給バランスに大きく左右されます。同じ方法で栽培しても毎年収穫量や品質が変動するため、価格もそれに伴い上下します。「豊作貧乏」という現象で、収穫量が多くても供給が増えすぎると価格が下がり、結果的に農家の収入が減少することもあります。一方、不作の年には品質が劣る作物でも高値で取引され、このような市場の不安定さが農業経営の大きな課題となっています。
さらに、農業従事者の高齢化や人手不足も深刻な問題です。地域全体で持続可能な農業を模索する必要があり、私たちは地元農家との連携を深めながら、安定供給と地域の農業発展に向けて取り組んでいます。
これまでの歩みと転機
家業に戻る前、私はいくつかの異業種で経験を積みました。その経験が現在の経営に非常に役立っています。当初は父との経営方針の違いなどから意見の衝突がありましたが、話し合いを重ねる中で次第に経営者としての自覚を持つようになりました。
2008年、父の長年の夢だった諫早湾干拓地での営農プロジェクトを開始しました。栽培面積を一気に5倍に拡大し、新しい市場への挑戦をめざすものです。しかし、干拓地への移動距離が長く、往復2時間以上かかるなど繁忙期には現場の負担が増加しました。また、拡大に伴い人手不足が深刻化し、さらには財務面でも大きな課題に直面しました。
ここで、当時のパートさんたちの状況について触れておきたいと思います。長崎の農業は、夏から秋にかけて閑散期に入ります。人件費を抑えるため、毎朝5時に、父がその日の必要人数だけパートさんたちに電話をかけるという方法を取っており、人によって出勤日数と給与に差が出ていました。パートさんたちはその日の仕事があるのかどうか、仕事の内容すら分からないまま待たされることが日常的で、このやり方に対する不満は少なくありませんでした。
そうした中、外国人技能実習生を受け入れ始めると状況が変わりました。彼らは常時雇用が条件となるため、これまでの不規則な雇用形態との調整が必要になり、これが会社全体の雇用形態を見直すきっかけとなりました。社内では、「自分たちの仕事が減るのでは」という誤解や反発もありましたが、結果的には会社全体の基盤を整える大きな転換点となりました。労務管理の整備が不可欠となり、就業規則や雇用条件通知書を社労士さんと一緒に作成するなど、ようやく「普通の会社」に近づき始めたと感じた瞬間でもありました。常時雇用のスタッフを確保できたことで計画的な人員配置が可能となり、現場での作業効率が徐々に向上。現場の雰囲気にも少しずつ変化が現れ、労働環境の整備によって社員たちが安心して働ける基盤が形成されていきました。この変化が、会社全体の成長を支える基礎になったと感じています。
多様性を生かす経営
現在、私たちの会社では、外国人技能実習生、高齢者、障害者など、さまざまなバックグラウンドを持つ社員が働いています。それぞれが自分の特性を生かし、役割を果たしながら業務を進めています。
外国人技能実習生は、言葉や文化の違いを克服しながら、真摯(しんし)に仕事に取り組んでいます。彼らの働きぶりは日本人社員にもよい影響を与え、社内全体のモチベーションを高めています。また、障害を持つ社員には、特性に応じた業務を割り当てることで、能力を最大限に発揮できる環境を整えています。
たとえば、知的障害を持つある社員は、最初は仕事の流れをつかむのに苦労しましたが、徐々に成長し、現在では農機具の操作や生産管理を任されるまでになりました。彼の成長を見守る中で、他の社員も彼を支えることの大切さに気づき、職場全体の連携が強化されました。また、高齢の社員には、農作業の指導や品質管理など豊富な経験を生かせる役割を与え、若い世代の育成に貢献してもらっています。年齢や能力の違いを超えた協力体制が構築されていきました。
今後の目標と挑戦
現在は事業規模を着実に拡大しながら新たな販路開拓に取り組み、野菜加工品の開発にも力を入れ、将来的には自社ブランドとしての商品展開をめざしています。また、中期的な目標として、北海道など他地域での事業展開を計画中です。繁忙期が異なる地域と連携することで、収益の安定化を図るとともに、日本全国での農業活性化に貢献したいと考えています。
わが社はさまざまな個性が集まる場です。生産者の皆さんも消費者の皆さんも、それぞれが個性や特性を持っています。同友会もまた、個性豊かな人々が集まる組織です。これらの個性や特性を「1つの灯」と例えるなら、その灯をどこまで広げていけるのかが問われるのだと思います。
1人の力で照らせる範囲は限られています。しかし、小さな灯が集まり、10、100、1万と増えることで、やがて大きな光となります。これは「一燈照隅、万燈照国」の精神そのものです。長崎同友会をはじめ、全国4万7500名の会員とその社員、ご家族までを含めれば、計り知れない力となるでしょう。
だからこそ、社員と思いを共有し、人を生かす経営を実践することが大切です。誰もが活躍できる環境をつくるために、私はこれからも関わるすべての方の架け橋であり続けたいと思います。
会社概要
設立:1984年
社員数:12名
事業内容:青果物卸売業
資本金:1,000万円
年商:3.6億円
URL:https://iidaseika-potato.com/
社名を社員さんが決める会社とは
“一人ひとりの思いが反映される会社へのING”
大分デバイステクノロジー(株) 代表取締役 安部 征吾氏(大分)
(大分同友会副代表理事・経営労働委員長)
わが社は、大手半導体メーカーが九州に進出し始めていた1970年、協力会社募集の記事を見た叔父と父親が共同代表で設立してスタートしました。私は1967年に生まれ、高校まで大分で過ごした後に関東の大学に進学し、大手電機メーカーに就職しました。そこで8年間を過ごしましたが、帰省した際に当時のわが社のナンバー2から「君は息子だから後継ぎとしての義務や使命があるのではないか。これからどうするつもりなのか」と問いかけられます。同時に会社がつぶれるかもしれない状態であることも知り、一念発起して31歳で入社しました。
後継ぎとして入社した当時
入社後は現場で技術系の仕事をしていましたが、1年ほど経ったある日、先代が脳梗塞で入院しました。そのとき初めて実印や土地の権利書などに触れ、何もかも分からない状態から、積まれていた過去の決算書をエクセルに入力していくうちに会社の状況が理解できました。そして、たまたま社長という役職に就くことになり、後ろ指をさされない正々堂々とした経営者になるという思いのもと、初めから対等な労使関係も意識していました。
ところが、社長に就任した2001年にITバブル崩壊が起こり、1億円を超える大赤字になりました。誰にも相談できずに恐怖を抱えている中、当時の代表理事から大分同友会を紹介され、わらにもすがる思いで入会しました。同友会は出世が早く、入会3年後に経営労働委員長、その後は社員教育委員長や支部長、地球環境委員長、障害者問題委員長、そして2023年から副代表理事兼経営労働委員長を務めています。たくさん役をやらせていただいたことは今日の財産になっています。
同友会で救われたこと
経営指針成文化セミナーと地球環境委員会が大きな転機となりました。成文化セミナーで経営理念について真剣に考えていくうちに、経営者としての覚悟ができたのは大きな経験です。また、経営戦略が重要であることにも気づきました。当時は大手半導体メーカーの下請けで、自分たちで売り上げなどが決められませんでした。
その後、地球環境委員会でSDGsや環境経営を学び、それが大きなヒントになって会社の方向性が明確になりました。太陽光パネルの設置や環境商材の販売など環境経営に取り組む中、本業であった半導体事業が省エネに寄与する存在、つまり地球環境に貢献できるものであると捉えられるようになり、強みを生かすために電力制御につながるパワー半導体という分野に事業をシフトしていきました。それによって自社で設計・開発まで行えるようになり、現在は特許も複数取得しています。
同友会での学びの実践
当初は自分1人で経営指針書を成文化していましたが、現在は社員と共に作成しています。各部門長が自部門ごとに売り上げ見込みや必要な人員、設備などの経費も検討してもらうことで、自部門への思いが強くなり、社員たちの責任感と本気度が大きく変わりました。現在は、売上高や当期利益、総資産、借入金、平均労務費などの数値情報もすべて社内で公開しています。
社員教育は、リーマンショックで大きく仕事が減少したときから毎日行い、必然的に教育体系ができあがっていきました。現在は年間計画表をつくり、講座名や求める人物像、研修内容まで全て経営指針書の中に入れ込んでいます。頑張って能力を付ければワンランク上の仕事ができ、役職が上がって部下を持つ、そうして人間的成長につながるようなキャリアマップを試行錯誤しながら更新しています。
また、社員が社長を評価する「社長アンケート」を毎年実施しています。「社長とのコミュニケーション」「社員を大切にしているか」「会社の働きやすさ」などの設問に「大変よい」「よい」「悪い」「大変悪い」のいずれかで回答してもらいますが、2023年度は全項目で前年より悪化していました。「働きやすくて雰囲気もよく、自分の成長も感じるが、将来設計ができない」という総括でした。社員たちの忌(き たん)憚(き たん)ない意見は胸に刺さりますが、それに対する回答を社長の約束として明確に示し、その後の行動に移すようにしています。
先代の時代から新卒採用にも取り組んでおり、のべ94名ほどが新卒で入社しています。大手が採用枠を増やして採用が難しくなっていますが、選ばれるためにはよい会社にすればいいのです。何も難しくありません。社員がやりがいを持って生き生きと働き、レベルアップできるような会社になれば採用にも困らないと思います。採用難というピンチがヒントになり、よい会社にするために働きやすい環境を整備していきました。多能工化や手順書の作成、5S活動などを通して生産性が向上し、大分県では第1号となるユースエール認定も取得しています。
今後の目標~同友会の活用について
もともとわが社は大手の下請け100%でしたが、約20年間で事業を再構築し、現在は50%まで減少しています。今後5年間はパワー半導体による攻めの経営で、売り上げを2・5倍にする計画です。2020年には新たな工場を増設し、会社の面積は1・7倍になりました。自社の周りに関係する他社の工場がたくさん建てられたら、地域の人口減少も防げるかもしれません。そんなわくわくする地域の姿も想像しながら、次々世代幹部候補となる若手社員と一緒に長期計画も作成しています。
経営指針書を作成し、人の部分にフォーカスすると必要な人材が見えてきますが、採用は簡単ではありませんので勉強が必要です。既存社員に成長してもらうための社員教育の学びも必要です。企業規模が拡大すると新たな人の問題が出てきますので、人間尊重の経営を障害者問題委員会で学ぶ、いろいろな役員を経験し、この学びのサイクルを回すことこそが人を生かす経営の本質だと感じています。
私は、会社は社員のものだと思っており、社名も社員が決めました。2024年の経営指針発表会は初めて全社員を集めて開催し、部門目標などは各社員が発表してくれました。私の出番がなくなり一抹の寂しさがありましたが、これこそ経営指針が社員の中に浸透してきている証だと感じています。これからも、半導体製造を通じて地球環境保全に寄与する会社をめざしていきます。
会社概要
設立:1973年
社員数:121名(パート・アルバイト含む)
事業内容:半導体アセンブリ事業、半導体試作、開発サポート事業、省エネ機器保守事業
資本金:2,400万円
年商:10億円
URL:https://www.odt.co.jp/
「中小企業家しんぶん」 2025年 2月 5日号より