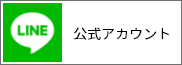「ゾンビ企業」が7年ぶりに減少
中小企業をめぐって最近変化が生まれています。1つは、本業の利益で借入金の利払いをまかなえない、いわゆる「ゾンビ企業」が7年ぶりに減ったことが分かったこと。2023年度は前年度に比べ13・0%減の約22万8000社となり、直近1年で3万4000社減少しました(帝国データバンク)。
一部の中小企業が原材料高を販売価格に転嫁し、資金難を脱したとされます。また、実質無利子・無担保のゼロゼロ融資の返済スタートが指標改善につながったと考えられています。
しかし、倒産や廃業による退出も減少につながったとみられます。東京商工リサーチによると2024年の倒産は11年ぶりに1万件を超えました。また、休廃業・解散した企業も6万2695件と2000年の調査開始以来で最多を更新しました(日本経済新聞、2025年1月21日)。中小企業の経営は時として死屍累々とした荒野を突き進むような心境ではないでしょうか。
大廃業の危機から大承継時代へ
中小企業をめぐる変化の2つ目は、大量廃業の危機の様相が変わってきていることです。後継者難を理由に、60万社に黒字廃業の可能性があるとした2019年の国の警告から5年が経過し、中小企業の事業承継が変わり始めました。創業家が所得と経営を分離して親族以外にバトンを渡す事例が増えています。
承継の際、誰が後継者になったかを帝国データバンクが調べたところ、2024年の同族承継は32・2%とデータがある2017年と比べ9・4ポイント下がりました。この間に生え抜きによる内部昇格が5・3ポイント増え、2024年は36・4%と同族承継を初めて上回ったのです。生え抜きによる承継は実績次第で社長になる可能性が広がり、社員のモチベーションを高めます。
内部昇格に加えМ&A(合弁・買収)型の継承も増えており、2024年は20%を超えました。ここで、後継者のいない中小企業の比率は2023年に54・5%と、2018年比で12・7ポイント下がっています。
柔軟な代替わりは成長への分かれ目です。東京商工リサーチによると、2019年に承継を実施した中小企業の純利益は3年後に平均で35・3%成長し、交代しなかった中小企業の約6倍に達しました。
大廃業の危機を大承継時代へ転じることができれば中小企業が支える日本経済の実力は一段と強くなります。
いま変化の土壌は整いつつあります。多彩な会社承継が日本経済の安定した土台を守り、イノベーション(革新)を産む可能性を高めるかもしれません(日本経済新聞、2024年12月15日)。
(U)
「中小企業家しんぶん」 2025年 2月 15日号より