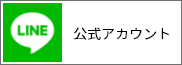足元では物価高や人手不足などの急激な社会変化がある中、中小企業の事業の継続・発展は日本経済の再生と成長に必要不可欠です。連載『新時代を切り拓く中小企業』では、目まぐるしく変化する時代にあってもチャレンジを続ける企業を紹介します。第15回は三和電気(株)(宮崎裕二代表取締役社長、東京同友会会員)の実践です。
三和電気(株)は、白熱電球用フィラメントの製造・販売を行う会社として1933年に創業されました。フィラメントは、家庭用白熱電球だけでなく自動車用電球やUV光源、半導体加熱源など幅広い分野で活用されています。ところが東日本大震災以降、省エネや節電などへの意識の高まりからLEDへの切り替えが急速に進み、市場縮小が続く業界でもあります。
そうした構造変化の中、宮崎氏は2013年に同社社長に就任。徹底的なコストカットを行う一方で、社員の雇用と給料を守りながら新たな事業づくりに取り組んできました。「人づくりがものづくりにつながる。経営指針成文化セミナー受講が転機となり、大切なことを同友会で学んできたからこそ」と振り返ります。
ニッチな存在として自社の強みを生かす
現在は、産業用機器と民生用機器、照明用機器の3分野を中心に、確かな特殊加工技術を顧客のニーズに合わせてカスタマイズすることで、あらゆる産業への事業展開を図っています。コロナ禍では、巣ごもり需要によって空気清浄機や電子機器関連部品のニーズが高まり、大手からの受注もあって生産量は一気に倍増。昼夜問わず工場を稼働させるなど、急激に生産体制を変更したにもかかわらず納期遅延や品質不良を出しませんでした。こうした対応は同社の信頼を高めるとともに、コストダウンやBCP対策など厳しい条件を乗り越えたことが企業体質強化にもつながりました。
事業構造転換を果たした2016年からは毎年昇給を実施し、賞与を年に3回支給するなど、社員への利益還元も忘れません。「社員の成長が業績に直結していることを繰り返し伝えている」と話す宮崎氏。収益構造を変化させ、新たな顧客を創造しながら新規開発や設備、人材への投資に挑戦し続けています。
全社員参加型の企業改善
近年はDX化を推進し、独自の基幹業務システムを立ち上げ、社内の情報共有はポータルサイトを活用し、社長をはじめ各社員のスケジュールや申請書類、進捗管理など必要な情報を集約しています。同システム上では全社員が改善提案、改善実施報告を出すこともでき、パート・派遣社員も含め年間600件ほどの提案と改善報告が上がります。年に2回改善表彰も行い、会社のことを自分事として捉えることで仕事の面白みを感じてもらい、社内活性化を図る仕組みです。
また、同社では毎年の新卒採用に加えてシニア世代も積極採用しており、幅広い年齢層の社員が活躍中です。約100名の社員のうち、15名が大手を定年退職した専門性の高いスキルを持つシニア社員で、これまで蓄積されてきたノウハウや技術を存分に発揮し、若手育成にも貢献しています。
新入社員には「新入社員教育プログラム」を整備し、大学・大学院卒の社員は半年間、高卒社員は3カ月間でものづくり会社として必要な知識を学びます。研修後には、2年間かけて職務の改善策を自ら見つけ、成果をまとめて役員・幹部社員に発表する教育プログラムも用意。講師役も社員たちで、毎年内容をブラッシュアップしながら自主的な活動が広がっています。
同社が発起人となった「燃えるインターンシップ」は、2週間を通して中小製造業の実態を知ってもらい、最終日に配属先企業の改善提案をプレゼンするという企画です。企業と学生が共に学び合う場になっており、事務局運営は長期インターンシップ生が担当。学生たちの姿は社員たちの大きな刺激となっており、若者同士の交流も活発になっています。
ものづくりの可能性は無限大
2022年7月、同社のマイクロコイルが「市販の最小メタルコイル」としてギネス世界記録に認定され、注目を集めました。コイルの外径は27マイクロメートル(0.027ミリメートル)と髪の毛の3分の1ほどの細さで、半導体の導通検査などで実際に使用されています。社員たちのモチベーションにつながるだけでなく、外部発信を通じた技術の継承も狙いの1つです。「自分の仕事が認められている実感を社員たちが持ち始めており、思い切って挑戦してよかった。ものづくりの面白さを発信し、人が集まる会社にしていきたい」と語る宮崎氏。三和電気は創業100周年を1つの通過点に、新たな価値を創造し続けます。
会社概要
創業:1933年
社員数:99名
事業内容:照明・医療・産業装置用コアパーツの開発・製造・販売
URL:https://mitsuwa-elec.co.jp/
「中小企業家しんぶん」 2025年 2月 15日号より