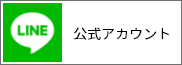中同協経営労働委員会は、毎年2~3月を「働く環境づくり強化月間」と定めています。本特集では、働く人にとって魅力ある、将来に夢の持てる企業をつくるために、働く環境づくりに積極的に取り組んでいる会員企業を紹介します。
社員の声を経営に反映させ、働きやすい職場環境へ
(株)カーサービス山形 代表取締役社長 小川 大輔氏(山形)
(株)カーサービス山形は、1980年に小川氏の父が中古車の卸売りとして創業し、2024年に45周年を迎えました。小川氏は21歳で同社に入社し、先代の急逝を受けて30歳の時に社長に就任しました。中古車業界ではカリスマと言われる存在だった父の後を引き継ぎ、社長業に悩みを抱えながら、当初は「赤字にさえしなければいい」「これまでと同じ売り上げと利益を出せればいい」という事なかれ主義の経営を続けていました。
過去の失敗
先代が亡くなり小川氏が社長に就任した2004年は、売り上げ・販売台数ともに過去最高の年でした。拡大路線を取り、人員配置や売り方など社長の理想に向けた改革を進めていきましたが、次第に売り上げが減少。原因はリーマンショックや消費増税など、当時は外部環境のことなど考えもせず社長独りよがりの社内改革を行ったためで、社内を見渡すと人が育っていませんでした。
採用計画や育成計画もなく、会社概要や就業規則の説明などが不十分なまま人材を採用し、入社間もない社員に「すぐに車を売ってください」「売れない営業は辞めても構わない」と伝えていたほどで、社員を育てる意識もありませんでした。
何より大事なのは経営者の覚悟
そんな中、2013年に同友会と出合います。先輩経営者から「1人でできることは限られている。できる人に仕事を任せ、働きやすい環境にするのが社長の仕事」と言われ、社長である自分にしかできない役割に気づきました。
まずはビジネスモデルを見直し、中古車販売をベースに、新車の販売から車検や点検などのアフターメンテナンスにつなげることに重きを置いた方針に転換。売り上げの7割を占めていた本社(山形店)は多忙を理由に退職者も出ていたことから、店舗ごとの売り上げ構成を見直して業務量を他店舗に分散することにも取り組みました。
2014年には経営指針を創る会を受講し、社員満足度調査も実施。社員からは「給料が安い」「休日が少ない、休みづらい」「有休がとれない」「みんなの向いている方向が違う」など率直な回答が出され、それらの意見を踏まえて2015年に最初の経営指針発表会を行いました。
その後、社員満足度調査の結果や社員と『企業変革支援プログラム』を活用して自社の課題を抽出し方策を検討の上、経営指針書に盛り込み、労働環境整備にも取り組んできました。その結果、売り上げ・利益とも右肩あがりになっていきました。
社員の要望から職場環境を改善
同社には、CS「顧客満足度向上」委員会、ES「従業員満足度向上」委員会、社内の整理・業務改善を行う「カイゼン委員会」の3つの社内委員会があり、全社員が参加してSNS戦略や社内教育制度の見直しなどを行っています。委員会での議論や社員アンケートを基に多彩な福利厚生を整備しており、その1つが資格取得支援制度。会社が受験費用を負担して意欲的に学びたい社員を支援し、準国家資格を取得した社員もいるほどです。
また、学ぶ機会をつくってほしいという社員の要望から実現したのが社内アカデミーです。社員たちの自主的な取り組みの1つで、英会話講座やリーダーシップ理論、電気自動車と再生可能エネルギーへの取り組みなど幅広いテーマで人間的成長を図る機会となっています。
さらに、DX化プロジェクトを発足させ、社内ポータルサイトを導入。全社員にPCやタブレットを支給し、情報共有の仕組みをつくって生産性向上を図っており、案件管理をはじめ、いつ誰がどんな商談をしているかを見える化しています。就業規則、労務管理、人事評価などもすべてポータルサイト上で完結させており、情報格差解消につなげています。
最大の地域貢献は社員共育
現在は新卒採用が中心です。採用前には職場体験を徹底してミスマッチ防止に取り組み、入社後には45日間の集合型研修、45日間の各店舗でのOJT研修を経て、本人の希望と各店の責任者の意向で配属先を決定しています。定期的な若手社員研修、人事評価制度の見直しやベースアップにも積極的に取り組んでいます。2021年から健康優良法人大規模法人部門を4年連続で獲得しています。
近年では再生可能エネルギーの活用にも取り組み、屋根が太陽光パネルとなったカーポートの販売も開始しています。自家発電や電気自動車への電力供給が可能で、冬季の雪よけだけでなく年間を通じてカーポートを活用することで、地域の人々の所得向上もめざしています。
「わが社の財産は人。とにかく社員の意見を聞いてどんな働き方がいいか模索してきた」と話す小川氏。経営指針に人を生かす経営の実践を盛り込み、自社の存在意義や役割を追求しながら、車を通じた地域発展へと邁(まい)進しています。
会社概要
創業:1980年
社員数:正社員161名、パート社員2名
事業内容:中古車・新車販売、オークション、車両整備などの車全般
URL:https://cs-yamagata.co.jp/
社員を大切にする企業文化のもと次の100年を見据える
アシザワ・ファインテック(株) 代表取締役社長 加藤 厚宏氏(千葉)
120年の歩み
アシザワ・ファインテック(株)は、ナノサイズまでの微粒子を作る機械を開発・製造・販売する微粉砕機メーカーです。1903年に東京で蘆澤(あしざわ)鐵工所として創業。80年には「ビーズミル」と呼ばれる微粉砕・分散機の技術を導入し、鉄工所からハイテク機械メーカーへ転換。社名もアシザワ(株)に変更しました。90年に千葉県に本社を移転し、2003年、創業100周年を機に現在のアシザワ・ファインテック(株)が設立されました。
再出発を象徴する取り組みとして、若手社員を中心とした「100年委員会」を設置。会社のあり方や人材育成について議論を重ねて『お客さま第一』や『環境整備』といった指針を定め、全社員でそれらの価値観を共有しました。この試みが今日の企業文化の基盤を築いています。
心理的安全性を重視した社員教育
採用活動では大手の採用支援サイトは使わず、大学の研究室や高校との関係を継続することで毎年安定的に新卒を確保しています。リーマンショックの際も採用活動を止めることはありませんでした。社員数は設立時60名から現在は160名に、また女性社員も5名から40名まで増加しました。選考過程では、学生に見学会を含めて少なくとも5回本社を訪問してもらい、同社の価値観に共感できるかを重視した採用を行っています。
入社後は、3カ月かけてすべての課を体験する「全課研修」を実施。新入社員が「どの部署でも安心して働ける」と感じられるよう、心理的安全性を確保した環境づくりに力を入れています。また、若手の中堅社員をメンターとして配置し、定期的なメンター会議で課題を共有。経営陣に相談すべきと判断された事項は経営会議で議論され、組織全体でメンターをバックアップする体制が整っています。「メンター制度を通じて管理職としての視点を養ってもらうことを期待しています」と人事総務課の宮下氏は語ります。
また、設立当初から続く社長と直接対話する「社長面接」や、毎月の朝礼での社長スピーチなど、社長と社員が顔を合わせる機会を設けています。これにより、全社的な方針の共有を図ると同時に、社員に「会社の一員である」という認識を深めてもらうことを大切にしています。
これらの取り組みの結果、直近3年間の定着率は100%を達成するなど、社員が安心して働ける環境が実現されています。
社員の声を反映して働きやすい職場へ
同社はユースエール認定や健康経営優良法人認定などを継続して取得しています。当初、社員から「本当に認定に値する会社なのか?」という声もありましたが、認定を維持することで、「その基準にふさわしい会社にならなくてはいけない」という意識が高まり、働きやすさを実現していく組織風土が形成されました。
ユースエール認定を取る以前は月平均40~50時間残業をする部署もありましたが、「不要な残業はしない」という全社的な取り組みにより、現在では月平均12時間程度にまで削減することができました。また、取引先の大手企業で働き方改革が進んだことや、ワークライフバランスを重視する若手社員の増加もこの変化を後押ししたと言います。さらに、社員の声を反映し、時短勤務や1時間単位の有給休暇取得を導入。コロナ禍を契機にテレワーク環境の整備を進めるなど、柔軟な働き方が推進されています。育児休暇の取得率は男女ともにほぼ100%を達成。「私も子どもの運動会や発表会のときは休みを取りました」と笑顔で語る加藤氏。「上司が率先して休んでくれると、家族を大事にすることをよしとする会社なんだと社員は実感することができます」と宮下氏は付け加えます。
また、社員の家族との親睦を深めるため、年に1回「家族親睦会」を実施しています。昨年はオリンピックイヤーにちなんで運動会を開催し、今年は会社見学会を予定しています。
未来への展望
同社は現在の粉砕機製造と微粒子加工に加え、自社の機械を活用した素材開発に着手する予定です。「私が入社したころはいいものをつくれば売れるだろうという考えの会社でしたが、指針を明確化し働き方改革を進めることで大きく変わりました」と加藤氏は振り返ります。
今後はお客さまから信頼され、相談される企業になることをめざし、競合他社との差別化を図ります。お客さま第一主義と働きやすさを両立させ、次の100年を見据えるアシザワ・ファインテック。その挑戦はまだ始まったばかりです。
会社概要
創業:1903年
社員数:160名
事業内容:機械製造業、材料の加工業
URL:https://ashizawa.com/
健康経営こそ人を生かす経営
松葉倉庫(株) 代表取締役 松葉 秀介氏(静岡)
倉庫・運送業を営む松葉倉庫(株)では、高齢者や障害者をはじめあらゆる社員が活躍しています。2022年に「健康経営優良法人(ブライト500)」を取得するなど、健康経営を通して安心して働ける職場環境づくりが進んでいます。
きっかけは物流業界の「職業病」
物流業界の職業病は「腰痛」。悩みを抱えるドライバーは多く、同社の大きな経営課題でした。そんな中、2014年に鍼灸マッサージ治療院を営む寺田卓正氏(静岡同友会会員)と健康アドバイザー契約を結び、社内で腰痛予防セミナーやストレッチなどに取り組み始めます。すると、徐々に腰痛改善が進んで急な欠勤などが減少。さらに、寺田氏は気軽に社員の悩みや相談にも乗ってくれ、心身ともに社員の健康を支える存在となっています。
また、同時期に導入したのが、生活習慣改善を後押しする「健康増進BANK」制度です。「ランニング」「水泳」「ゴルフ」など日々の運動時間を記入し、「睡眠」「入浴」「禁煙」などの生活習慣と合わせて点数化して、累計点に応じて奨励金を支給する制度です。生活習慣の見える化によって、社員の健康意識も高まっていきました。
取り組み始めた当初はまだ健康経営という言葉が一般的ではなかったため、業界の全国紙や専門誌に取り上げられるなど注目を集めました。「健康でないといい仕事はできず、いい会社にならない。経営課題解決が出発点となり、結果として健康経営につながった」と振り返ります。
働く親を支援したい
同社は、企業主導型保育園「まつの実」を運営しています。企業主導型保育園は、企業内や隣接地に設置される認可外保育園で、待機児童解消を目的に2016年に始まった国の事業。そのわずか2年後の2018年、藤枝市内第1号として設立された「まつの実」は、内閣府のホームページで先行事例として紹介されるほど先進的な取り組みです。
同社の社員をはじめ周辺企業の社員も利用しており、地域の人々の仕事と子育ての両立支援に貢献しています。また、保護者向けにマネー講座やヨガ教室などを行う「ママゼミ」を実施して親同士が交流できるようにしており、地域のコミュニティの場ともなっています。同社の倉庫や駐車場などは園児たちの散歩コースです。自社に親しんでもらうことで物流業界に興味や関心を持ってほしいとの思いもあり、「ゼロ歳からのキャリア教育」だと話します。さらには、国の基準よりも多くの保育士を配置することで、保育園で働くスタッフの労働環境も整備しています。
もともと結婚や出産を機に退職する社員が多く、子育て支援が同社の課題でした。職場の近くに保育施設があれば安心して出産や育児ができます。現在では、産休や育休取得後の職場復帰が当たり前の企業風土が出来上がっており、社員の職場満足度とともに定着率も向上しています。
2024年問題ピンチか、チャンスか
物流センターには太陽光発電設備が設置され、自社が使用する電力の多くは再生可能エネルギーで賄っています。非常用発電装置によって非常時でも業務が継続でき、地域にも電力を供給できるようにしています。また、2024年には新たな物流倉庫を竣工(しゅんこう)しました。重視したのは立地です。インターチェンジの近くに建設し、関東圏や関西圏などに素早く運搬できるようにしました。新倉庫のアクセスのよさは通いやすさにもつながり、社員の通勤ストレスも解消。立地も健康経営だと言います。多発する災害や脱炭素社会実現に向けた世界的な潮流、サプライチェーンの変化、いわゆる「2024年問題」など自社や業界を取り巻く環境が大きく変化している中、未来に向けた投資を行う松葉氏の姿勢は社員に安心感を与える無言のメッセージです。
「長く働いてもらうためには、体だけでなく心の健康も重要。人生設計や金銭面、会社の将来など人によってさまざまな不安を抱えている。健康経営はすべての経営課題・戦略と密接で、人口減少などの地域課題解決に向けた取り組みでもある。健康経営こそが人を生かす経営の実践であり、何よりも経営者自身が健康であることが重要だと思います」と語る松葉氏。生き生きと働く社員たちとともに、新たな時代を展望しています。
会社概要
設立:1972年
社員数:110名
事業内容:倉庫・運送業、保育事業、太陽光発電事業
URL:https://www.matsuba-soko.co.jp/
まつの実:https://matsunomi-hoikuen.jp/
「中小企業家しんぶん」 2025年 2月 15日号より