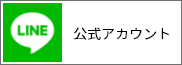中同協企業環境研究センター(略称・研究センター)で全国の同友会会員対象企業の協力のもと年4回実施している「同友会景況調査(DOR)」の報告書には、研究センター委員が執筆を担当するコラム「DORの眼」が掲載されています。今回はその「DORの眼」から、1月31日発表のDOR152号掲載の「『借入がないので金利上昇とは無縁』などということはない」を紹介します。
DORに見られるように、借入金利の急上昇が昨年から続いている。金融機関から借り入れのない企業も増えつつあるとはいえ、その動向に気をもんでいる経営者も少なくないだろう。そんな時に金利のなかった過去を振り返る意味はないとの誹(そし)りを受けるやもしれないが、昨年末に日本銀行から過去25年の金融政策に関する報告書(「金融政策の多角的レビュー」)が出されたので、特に2013年以降の大規模緩和を日本銀行がどのように評価しているのか、まずはその紹介から始めたい。
簡単に言えば2013年以降の金融政策に対する総体的結論は、「当初想定したほどの物価上押し効果は発揮しなかったが、経済・物価を一定程度押し上げる効果があった」というものである。大規模緩和を実施しなかった場合に比べてGDP水準を1・3~1・8%(成長率を押し上げたのでない点に注意)、消費者物価を前年比で+0・5~0・7%ポイント押し上げたとの試算がその根拠である。政策効果としてこの数字が高いか低いかを論じる紙幅はなく、かつ効果を検証する論点はいくつもあるが、銀行とその貸し出しについて見ておけば、日本銀行は、大規模な金融緩和がなかった場合に比べて「貸出残高は増加した」としており、金融要因によって3%弱、貸出残高が押し上げられたと見ている。
さてこの貸し出しは何に向けられたのか。以下は、筆者による計算である。
銀行・信用金庫の貸出金残高は、2013年第14半期の487兆円から2024年第34半期には680兆円にまで約40%増えた。これを貸出先別に見ると、同期間に増えた製造業向け貸し出しは21%に過ぎないが、不動産業は67%も増大している。住宅ローンを主とする対個人貸し出しは33%の増加で、上記3つを除いた残りの貸出金残高の増加率も37%なので、この間、不動産業への貸し出しが突出していたことがわかろう。対中小企業貸出だけを取り出してみても、製造業向けが17%の増加であったのに対し、不動産向けのそれは71%であったから、中小企業向け貸し出しの拡大を牽引(けんいん)したのも不動産業であった。
現在までのところ、借入金利の急上昇が深刻な事態を引き起こしているわけではなく、返済負担増による収益・資金繰りの悪化を訴える声は、DORでも小さい。また、仮に金利が上昇しても設備投資に与える影響はかつてに比べてかなり小さいとの研究報告もある。なぜか? 借金がない企業の増加といった理由のほか、これらの背景には資金借り入れを増やした業種の「偏り」があるのかもしれない。しかし借り入れがないからと安心はできない。借り入れがあろうがなかろうが、金利の変化は経済社会の基礎であるから、自社の借り入れ負担は変わらずとも、基礎が変われば取引先や市場の環境はガラッと変わり得る。指標悪化に気づいてから、その先を考えるのでは遅い。約30年ぶりの環境変化に目を凝らし、DOR今号の見出し通り、変化の中で「自社の立ち位置」を再考する2025年でありたい。
「中小企業家しんぶん」 2025年 2月 15日号より