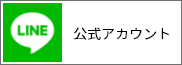連載「わが社のSDGs」では、経営理念をもとにSDGsに取り組む企業の事例を紹介します。第21回は、関西クリアセンター(株)(伊山雄太専務取締役、大阪同友会会員)の取り組みです。
創業から現在までの歩み
関西クリアセンター(株)は1965年に伊山氏の曾祖父が創立した「伊山商店」を前身とする産業廃棄物処理業者です。創業当初は糸くずの回収を主力事業としていましたが、祖父が引き継いだ後、金属くずの回収に軸足を移しました。
1999年に成立したダイオキシン対策特別措置法により、同社の金属処理用の焼却炉の運用が困難となり、新たに汚泥処理を主力事業とすることを決定。社員数は当初の2~3名から、汚泥処理事業の本格化に伴い20名へと増加しました。2020年には国内屈指の処理能力を誇る泉州プラントを竣工(しゅんこう)し、現在では約70名の社員を雇用するまでに成長しています。
同友会での学びを自社の組織づくりに生かす
後継者として入社した伊山氏は、当初、社員との関係が悪化し、社員の約半数が退社するという事態に直面。財政状態も厳しく、債務超過が懸念される状況でした。同社の会計顧問から経営の勉強をしたほうがいいと言われ、ネット検索で見つけた同友会に入会。支部で増強委員を経て支部長を務める中で、「社員よりも会員と意見を調整することが難しく、そこで学んだ納得感のある合意形成のやり方を自社に活用することができた」と語ります。また、同時期に指針セミナーを受講したり、会員から経営実践を聞いたりすることで経営の学びを深めることができました。
環境へ配慮しつつ事業を拡大
同社は2006年にISO14001認証、24年にはエコアクション21を取得。産廃業界の特徴として、環境への配慮は欠かせないと言います。また、災害廃棄物処理にも取り組み、災害発生時には真っ先に現地に赴き、復旧活動に従事する役割を担っています。今年5月には、生物処理施設(水中に存在する生物を利用して汚水、排水を処理)を泉州プラントに完成させる予定です。水道局並みの設備を備えており、災害時には社員に水を提供することができるよう整備しています。
DX推進で業務改善
コロナ禍以前からDXに着手した同社は、ビジネスチャットツール「LINE WORKS」を導入。最初は社内から反対の声もありましたが、「誰もがスマホを持っている時代なのですぐに慣れるはずだ」と判断し運用を始めました。また、営業社員のデスクにはパソコンを置かず、クラウド型サーバーを採用することで外でも業務が進められる環境を構築。さらに、ペーパーレス化や電子契約も進めています。IT部門にはプログラマー2名を配置し、社内ツールの開発や販売を視野に入れた取り組みも進行中です。「いまだアナログが主流の産廃業界では、うちのDXはトップクラスだと思う」と伊山氏は言います。
計画的な採用と社員教育
採用活動ではホームページとハローワークを活用しつつ、取引先や社員からの紹介を通じた採用も行っており、将来の事業展開を見据えて余裕を持って人員を確保しています。また、ベトナム人社員を7名採用しており、中には日本人幹部と同等の待遇の社員もいます。
社員教育では、決算書の読み方を学べるマネジメントゲームを導入しており、原価計算は部署ごとに社員が行っています。半年に1度の面談ではそれぞれの要望を聞き、社員が学びたいことを実現する体制を整えています。
今後の展望
事業領域を広げ、顧客基盤を拡大してきた同社は、売り上げ50億円をめざし、M&Aや設備投資を積極的に進めています。伊山氏は「メーカーは資源確保に動き始めており、技術革新を続けていかなければならない。大手とは異なる戦略で事業を展開し、社員教育を通じて1人当たりの付加価値の最大化を図りつつ、労働分配率の向上をめざしたい」と語ります。
先々を見据えた事業展開と社員の成長を両輪とした挑戦を続ける同社の今後に期待が高まります。
会社概要
創立:1965年
社員数:71名(子会社含む)
事業内容:産業廃棄物の収集運搬、中間処理、土木建設工事、金属リサイクル
URL:https://www.kansai-cc.com/
「中小企業家しんぶん」 2025年 2月 25日号より