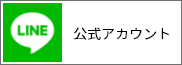2024年11月14~15日に開催された「第8回人を生かす経営全国交流会in長崎」でのパネルディスカッションの内容を紹介します。
パネリスト
(株)山田製作所代表取締役会長/中同協経営労働委員長 山田 茂氏
(株)EVENTOS代表取締役/中同協共同求人委員長 川中 英章氏
岡山トヨタ自動車(株)代表取締役社長/中同協社員教育委員長 梶谷 俊介氏
(株)マスカット薬局代表取締役/中同協障害者問題委員長 高橋 正志氏
コーディネーター
香川県ケアマネジメントセンター(株)代表取締役/中同協経営労働副委員長 林 哲也氏
林 いまから50年ほど前、1975年は史上最高となる32・8%の賃上げが行われました。その前年に第4回中小企業問題全国研究集会がこの長崎の地で開催され、大幅な賃上げにどう挑んでいくのかを議論し、翌年に労使見解が発表されました。それから50年を経て、同じ長崎の地で労使見解の精神に基づく人間尊重の経営について議論されるのが本日のポイントです。4委員会が連携して人を生かす経営を推進し、よりよい社会に向かうために何が必要かを考えていきたいと思います。
パネリストの自己紹介
山田 わが社はステンレス板の加工や溶接がコアの技術で、1品ものの産業用機械を作っています。直近2年間の賃上げについては、定期昇給とベースアップを合わせて、社員平均で昨年は5・1%、今年は4・8%の賃上げを行いました。しかし、国が定める最低賃金がどんどん上がる中、初任給(社内最低賃金)との差がなくなってきていることが目の前の経営課題です。地元の支援学校の生徒が来春に入社してくれることになり、わが社でも本格的な障害者雇用がスタートします。うれしい悩みではありますが、そうした18歳の社員と若手社員との差をどう考えるか悩んでいるところです。労使見解には、経営者の責任として「経営全般について明確な指針をつくることがなによりも大切」と書かれています。まずは賃上げの原資を確実に確保するためにどうするのか。さらに付加価値を上げられる会社に変化できるような取り組みを進めています。
梶谷 わが社はトヨタ自動車の方針に左右されることがしばしばありますが、自動車そのものの進化やカーボンニュートラルに向けたCO2削減への対応も求められています。やはり大きな課題は人口減少への対応です。自動車の台数は徐々に減少し、採用も難しくなっている中では働く環境の整備も重要です。
そうした中、自社が地域でどんな価値を生み出せるのか、お客さまや地域の課題を解決するために何ができるかを、社員と共に一生懸命考えています。学校での出前授業や地元企業とコラボした商品づくりなどいろいろなことに取り組んでおり、店舗という資源を地域のコミュニティに開きながら、活動を発信することで若者に入社したいと思われる企業になりたいと思っています。事業の可能性を広げていくために、自社のSDGs宣言を作成し、それに基づいた方針のもと実行しています。
川中 わが社の事業内容はわかりやすく言うと仕出し屋さんですが、パーティーが専門のためコロナは抜群に効き、売り上げは95%ダウンしました。その後回復し、今期の決算を終えるとコロナ禍で失った損失を全て払拭(ふっしょく)でき、自己資本比率も約60%に戻る予定です。採用活動を通した気づきの1つは、「飲食業とはこういう世界だ」という思い込みがあることです。業界独特の収益構造や働き方があるのは事実ですが、それは経営次第で何とかなりますので、2つのビジョン「地域の同業他社の方々のサービス向上に革新的な刺激を与えることができる会社になる」「食を愛する私たちが食を通して心いっぱいの幸せをつかむ」を掲げて経営しています。
わが社の特徴の1つは、パート社員の中にも店長や管理職がいることです。雇用形態によって身分が変わらないことを誇りにしてきましたが、この11月は賃金が上がり過ぎたため労働力不足になっています。収入の壁によって、忙しくなる時期に多くのパートさんが休んでしまいますので、この問題は本当に身に迫ってきています。
高橋 私は岡山県内に薬局を15店舗展開しています。医療業界や福祉を取り巻く経営環境は年々厳しくなっており、廃業やM&Aも増えてきましたが、わが社に大きな影響がなかったのは同友会のおかげです。入会後すぐに経営指針を成文化し、10年ビジョン達成のための単年度事業計画を毎年作成して、PDCAを回してきました。また、岡山同友会の社員教育大学や幹部社員大学などに社員と一緒に参加して、1人ずつ幹部社員を育ててきました。わが社の特徴はメンター制度で、先輩社員が新人の悩みを聞きながら1人1人に寄り添った教育をしています。この制度を入れてから離職はほとんどなくなりました。インターンシップも積極的に受け入れ、毎年3名ほど新卒薬剤師を採用しています。
16年前、岡山同友会の初代障害者問題委員長に就任した際に、赤石さん(中同協元会長)から経営の原点とも言える人間尊重の経営を学んだことが、現在の私にとっての最大の原動力になっています。「自主・民主・連帯」の精神を学び、執筆された書籍は繰り返し読んできました。わが社の理念は「命のある企業」です。社員を機械の歯車のように扱うのではなく、人間の身体のような血の通った温かい会社をめざして経営しています。
社会課題や地域課題と、企業づくりの新しいステージ
林 21世紀型中小企業のためには、社会的使命感に燃えた企業づくりが重要です。各委員会ではさまざまな活動が展開されていますが、企業活動を通した社会や地域課題の解決という視点で深めていきたいと思います。
高橋 わが社の目的・使命は、地域の1人1人の生命と健康を守って幸せな社会を創造することです。かけがえのない命を大切にしたい、健康であり続けたいという全ての人が持つ願いに応えるために、体も心も健康な地域づくりに取り組んでいます。地域の人々が健康になれば薬は売れなくなり、薬局の利益は下がります。しかし、社会保障制度の崩壊はまさに日本が直面している大きな社会課題であり、障害者問題も地域の社会課題の1つです。そうした課題解決のため、薬局の待合室では支援学校の生徒が心を込めて作った「さをり織り」や備前焼、ジーンズ生地で作ったエコバッグなどを販売しており、飛ぶように売れています。障害者雇用に限らず、あらゆる形で困っている人を支援することが重要ではないでしょうか。
障害者も含めて全ての命は平等であり、人間の命の重さに違いはありません。これを指し示しているのが「自主・民主・連帯」の精神の第3層「生命の尊厳性の尊重」です。こうした価値観を持つことが、よりよい社会を実現するための同友会運動の新しいステージではないかと思います。
川中 働きやすい会社にするためには、もうかりやすいことが絶対条件です。ですから、商品力に注力して利益が出る会社をつくり、その利益を人材育成や労働条件改善に投資していくべきで、未来の見えるビジョンづくりに今こそ取り組んでほしいと思います。現在はスカウト型の就活が主流になっていますが、それが通用する時代は続きません。自社の存在価値をアピールして、まさに選ばれる会社になるという観点を深めていくことが重要です。
飲食業の観点からは、人通りが多くもうかりそうな場所、つまり家賃が高い場所にお店を出すのがセオリーですが、例えば500円のパンを買うために、人はわざわざ高速道路に乗って買いに行くのです。それくらい食の世界には人を引き付ける力があり、これが業界の強みです。ですから、自分自身が目的地になり、困っている地域に勇気を持って出店することが地域づくりにつながると思います。わが社の売り上げに占める家賃の割合はわずか2%です。だからこそ、労働分配率が60%もありながら利益も出せるわけです。学生たちには飲食業界ならではの大変さもきちんと伝え、他の業界を勧めることもあります。学生の選択肢を広げてあげながら、それでも選ばれる会社になりたいと思っています。
梶谷 社員が誇りを持って生きている姿勢を、親として子どもに見せられているでしょうか。東京一極集中が進む中、都市部を除くほとんどの地域で若者人口が流出しています。若者たちが、地域を何とかしてやろう、この地で創業してやろうと思わなければ地方創生にはつながりません。われわれ経営者が社員と共に地域のために取り組むことで、一生懸命活動する親の姿を見た子どもにも意欲が出てくると思います。子どもたちの「こうしたい」という思いをいかに大人がサポートできるかです。
ある高校生に「私にとって一番身近なのは東京。地元に一番縁がありません」と言われ、いかに地域と関わっていないかを突き付けられました。他の高校生には「次世代、次世代とわれわれにばかり責任を押しつけるな。大人の方が金も時間もあるだろう」とも言われました。子どもたちのサポートができる大人を企業の内外に増やし、共に育ち合う関係づくりをすることがこれからの社員教育の大きなテーマだと思っています。
山田 わが社は大東市という大阪のものづくり地域にあります。ものづくり業界の皆さんの課題はやはり求人難で、わが社も毎年の新卒採用が難しくなっています。
わが社の大きな特徴は、徹底した整理・整頓・清掃で有名で海外からも含めて年間200社ほど工場見学に来てくれます。現在大阪では、来年開催される万博に向けてファクトリーツーリズムが盛んで、ものづくり企業ではオープンファクトリーに注力しています。参加者の99%が親子連れですので、自社の技術や製品の紹介だけではなく、ものづくり体験教室のようなことを各社が実施して、地域の子どもと企業をつなぐ活動になっています。加えて、地域にどんな仕事があるのかを親である地域の大人に伝えられることも大きな意義です。大阪同友会の中河内ブロックでは、企業説明会ではなく仕事説明会として高校1年生や2年生に地域にどんな仕事があるのかを伝える活動をしており、こうした実践が同友会運動の新しいステージにつながると実感しています。取り組む意義を社員と話し合い、自社にできることを検討することが、経営指針に社会課題や地域課題を位置づけるということだと思います。
共育と賃上げで働きがいのある企業づくり
林 4委員会の役割が大きいことを確認したうえで、共育と賃上げで働きがいのある企業づくりをどう進めていくかを考えていきたいと思います。
山田 限界利益を上げる方法は、変動費を下げるか売り上げを上げるかの2つです。わが社では変動費を下げる努力は絶えずしていますので、あとは高く売るしかありません。
数年前に、あるお客さんからかなり厳しい納期で1台760万円の乾燥機3台の注文がありました。無理をして受注して納めましたが、全くもうかりませんでした。その3年後に全く同じ仕事が来たときには「840万円にさせてください。しかも1台しかできません」と正直に言いました。それでも注文が来たのです。なぜかと言うと、変動費と固定費をしっかり分けた変動損益計算書を示して説明したからです。工場見学をしてもらった上で取引を始めるという関係を作っていた背景もあります。経営指針を社員と共に実践していくことが重要です。数字を用いてしっかりとお客さんに説明することが経営指針の今できる実践であり、賃金にもいい影響を与えていくと思っています。
梶谷 社員たちが誇りを持って生きていることが価値を生み出すのだと思います。魅力的な人間に育ち合い、「他で買うと私と付き合えなくなりますよ」とお客さんに言えるかどうかが、価格転嫁の面でも重要になってくると思います。経営理念と自身の生きざまが一致し、持ち味を生かしながら自主的な挑戦をしている社員には、お客さんが付いてきてくれます。人間らしく誇りを持って生きていくためには、経営者が「認めてくれないお客さんとは無理に付き合わなくていい」と言える覚悟も必要です。苦手な部分を補い合い、違いを生かしながら企業の価値を生み出していくことが、賃上げや働きがいのある企業づくりにつながると思います。経営理念をしっかり掲げ、共感してくれるお客さまや地域の方々を増やしながら、対等な関係で共によりよい社会をつくっていくことが重要です。
川中 労働は生きるための手段であることは間違いありませんが、生きる手応えを味わうものでもあります。この部分を社員と共有できると、「もっといい商品を作りたい」と思ってくれるようになります。これが人間らしく生きるということであり、認められたい、もっといいものを作りたいという思いは付加価値につながります。飲食業では、お客さまが食事を終えたときにどんな気持ちになれるのかを考えること、例えば「とりあえず生」という人に対して「シャンパンはいかがですか?」と、喉の渇きを潤したいという欲求に対していろいろなメニューを提示することが付加価値です。そのように、お客さまが何に困って自社の商品に手を伸ばしているのかに気づく過程が、自社の存在価値に気づくという共育だと考えています。なくてはならない存在になるために何が必要かを追求し、粗利を高めていくと賃上げにもつながります。そうした数字的な理解もしながら、どんな努力が必要かを一緒に悩み苦しんでいくことも共育だと思います。
高橋 今年は就労継続支援A型事業所の基本報酬が4割も削減され、事業所の廃止やB型事業所に移行せざるを得ないケースが増えています。能力があるにもかかわらず、最低賃金を保障してくれる働く場がなくなってきているのです。障害者雇用をしている企業に共通しているのは、思いやりのある文化があることです。障害者問題は経営の原点に立ち返るテーマであり、人間尊重経営をめざす同友会だからこそ取り組めるのです。
私たちがめざしているのは「幸せの見える共生社会」です。物は豊かになり、技術は進化して私たちの生活は豊かになってきました。医療技術も進歩し、がんでも治るようになりました。一方で、心の病はどんどん増えて低年齢化しています。昨年の児童・生徒の自殺者は513名で、1日に1人から2人の子どもが自殺しています。果たして私たち人類は幸せになったのでしょうか。同友会の深い理念を学び、すべての人を大切にした経営をすることが人生の豊かさを実現させると思っています。
各委員会から見た運動課題
林 全国で4委員会の総合力を発揮し、人間尊重の経営を推進してよい会社をつくり、よりよい社会をつくるという壮大なテーマがこの交流会に課せられています。4委員会の連携を進めていく上で、各委員会の課題をお話しいただきたいと思います。
高橋 「自主・民主・連帯」の精神の根幹となる「生きる、くらしを守る、人間らしく生きる」を学んでいるのが障害者問題委員会ですが、関心のある経営者が少ないことが課題です。かつて、ノーベル平和賞を受賞したマザーテレサは「無関心が一番の罪である」と言いました。さらに「愛の反対は憎しみではなく、無関心だ」とも言っています。スラム街の路上で絶望と悲しみに苦しむ人がたくさんいる中、見て見ぬふりをして声すらかけないこと、この無関心が一番の大きな罪だと言ったのです。
私はこの4委員会で学び、実践したことで利益も上がり、離職率も下がって新卒の薬剤師も採用できるようになりました。まず関心を持ってもらい、活動に参加して、人間尊重経営の根底を学んでいただきたいと思います。
川中 経営指針書を作っても引き出しにしまったままの方が多いと思います。そういう方の目標数値はほとんどが105%で、人を増やさなければ安心の数字ですが、そうした経営者の志の低さを見て、未来が見えなくなって社員は辞めるのです。現在はたくさんの学生が自社のブースに来る時代ではありません。まずはインターンシップを受け入れ、自社の至らない点を知るべきです。皆さんが地域で元気よく仕事をしていること自体が地域貢献であり、1人でも採用する努力をしたらどんな地域に変わっていくでしょうか。まずは飛び込んでみて自社の至らなさに気づき、そして再度経営指針に取り組むと、志高く数値も上向きなものがつくれると思います。
実は、昨日妻ががんの手術をしました。私の娘は2人とも知的障害を抱えていますが、1週間の有給休暇を取り、「私が頑張らないといけない」と輝きながら母親の看病をしています。人のために何かをするのは生まれて初めてで、あてにするから元気が出るのです。荷物が重たいから力が出ないのではなく、力を出せば荷物は持ち上がる。そういう観点で4委員会の連携が進むと、まさに「未来を見せる経営」を実践する企業が増えていくと思います。
梶谷 大久保尚孝氏(初代中同協社員教育委員長)は、同友会の社員教育の根幹について「人間の尊厳とは何か、人権とは何か、人間らしいとはどのようなものか、人間と社会との関わり、人間と自然とのつながり、人間としての幸せとはなど、人間が安心して暮らしていくために考えておくべき重要なテーマに沿って、労使が共に問い続けることを忘れてはならない」と語っています。この問いは、経営指針や理念を作成する際にも必ず考えておく必要があると思います。人間尊重経営のためには、経営者と社員が対等な関係で「人間とは何か」を問い続け、それを経営理念に表現し、方針・計画・ビジョンに落とし込むこと。そして、お互いをあてにし、あてにされながら生きられる企業をつくり、他社や行政などともあてにし合いながら社会をつくっていくことが必要です。それは共同求人や障害者雇用にもつながりますから、「人とは何か、人の幸せとは何か」を4委員会で議論していくことで、よりよい社会の実現につながると思います。
山田 同友会でいう三位一体の経営はカメラの3脚だと学びました。1本だけが伸びても倒れてしまいます。3本の足がじわじわと順番に伸びないといけません。工場見学やインターンシップは採用に向けた取り組みですが、社長ではなく社員が1から全部企画してくれています。この取り組みがまさしく社員共育です。経営指針の成文化と全社的実践を具体化し、障害者雇用も含めた三位一体をいかに自社で実践するかだと思います。労使見解は同友会運動すべてのベースであり、経営指針は三位一体の経営を前に進めていくためのツールです。
また、『企業変革支援プログラムVer.2』は、経営労働委員会だけでなく4委員会が集まって作られました。1つ1つ取り組んでいくと4委員会が重なり合っていることが分かり、三位一体の重要性に気づきますので、さらに活用を広めていきたいと思います。同友会運動を進めるためには、まず自社をよい会社にしなければいけません。そのために4委員会があり、自社経営全般を経営指針に位置づけることが重要だと思います。
これからの行動提起
山田 労使見解は、労使紛争が激化して自ら命を絶つ経営者もいた時代に、一切の愚痴を飲み込み、経営者の矜持にかけて責任を果たしていくのだと編纂されました。この矜持が書かれているのが、赤石さんの『生きる、くらしを守る、人間らしく生きる』で、「経営者の生きざまとは、経営にあたっては倫理ではなく事実である」と示しています。この事実という部分をしっかりと捉える必要があります。各地同友会の活動が労使見解の読み合わせで終わっていないでしょうか。自社の事例を用いて労使見解を語り合いましょう。そして、労使見解の精神に基づく経営指針の成文化と、実践企業を地域に増やしていくことが私たちに求められています。
『企業変革支援プログラム』は、労使見解が経営者に何を問うているのかを示しています。11~12月はe.doyu登録強化月間ですので、この交流会をきっかけに登録数がどんどん増えることを楽しみにしています。それから、賃金を含め働く環境を改めて見直し、整備することも重要です。時給1500円になった場合のシミュレーションもしておきましょう。
梶谷 中小企業家が地域の教育に積極的に関わり、持続可能な地域をつくることです。地域の教育現場で、人間とは何か、「自主・民主・連帯」の精神に基づく人間尊重とは何なのかを生きざまを通して伝えていくことが非常に重要だと思います。それによって、子どもたちが地域の可能性を見いだし、よりよい地域をつくるという覚悟を決めてくれるかもしれません。そうした志を持つ若者を企業に入る前から育てる活動が重要です。
そのためにも、まずは経営者と社員が人間として共に学び、育ち合うという同友会らしい社員教育の輪を広げる必要があります。人間とは何か、幸せとは何か、よりよい社会とは何かを問いかけながら、人間として育ち合うことのできる風土を広げていくことです。経営理念のもとに多様な社員1人1人が自ら成長しながら自主性を発揮し、お互いに共に成長していける、そして社会から認められる企業づくりへとつなげることが重要で、経営指針の実践は社員教育そのものだと思います。
川中 共同求人は外部発信の場です。皆さんが外部発信することで、「同友会は地域のために若者を残してよい地域づくりをしようと頑張っている。自分も入会して参加したい」という人が必ず出てきます。これが共同求人を通したよりよい社会づくりです。
今の学生はどんどん選択肢を狭められ、約6割が転職サイトに登録した状態で入社式を迎えているのが事実です。それでも、「もう少し働いてみよう」と思ううちに技術が身につき、お客さまからありがとうの言葉をいただいて、やりがいを感じて人間らしく生きている実感を持てれば、「人生を過ごす価値のある会社だから続けよう」と思ってもらえるはずです。
すぐに結果は出ません。4委員会の活動を1つずつかみ砕きながら全てに取り組むことで、やっと採用できる会社になるのです。ですから、まずは『企業変革支援プログラム』で自社の誇りを明確にしましょう。その誇りを共有し、みんなで外部発信をしながら、若者に対して地域にとどまる価値があると思われる会社・地域にしていきましょう。
高橋 障害者問題委員会では、障害者と健常者が共に生きて働ける社会について学び合っており、障害者雇用を通じた経営者や社員の変化などの事例がたくさん報告されています。ぜひそうした報告を聞いて関心を深めていただき、経営や生き方を変えていただきたいと思います。本日の学びを持ち帰って各同友会で広げていただき、皆さん1人1人が語り部になってほしいと思います。
先日、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞しました。最も障害者を生んでいるのが戦争であり、まったく罪のない人の命が失われ、多くの身体障害や精神障害を生み出しています。
「自主・民主・連帯」の精神の第3層には世界平和まで書かれており、これは同友会だけでなく万民のための理念です。だから難しく、奥深いのです。少しずつ勉強して、全ての人が幸せになる社会、そして平和な世界を実現することが私たち人類に課せられた大きな使命だと思います。
林 「自主・民主・連帯」の精神のもと取り組んできた同友会の現在の立ち位置に誇りを感じます。21世紀型中小企業をめざすためには、自社の地域での立ち位置と社会的役割を考えていく必要があり、自社の存在価値を考え直すという視点が求められます。その基礎になっているのが4委員会のたゆまぬ努力です。お互いをあてにし合いながら、よりよい社会の実現のために、4委員会が総合力を発揮できる環境をつくっていきましょう。
「中小企業家しんぶん」 2025年 3月 15日号より