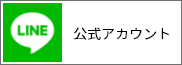ニッセイ基礎研究所「基礎研レター」の「気候変動と食品ロス・廃棄物削減」(2025年2月4日)というレポートによると、消費者がすぐに貢献できる気候変動対策の1つが、食品の廃棄物やロスを削減することだとされています。
消費者庁の2022年度のデータ(表1)によると、食品ロスがもたらす経済損失は約4.0兆円で、国民1人当たり年間32,125円の損失に相当します。また、食品ロスによる温室効果ガス排出量はCO2換算で1,046万トンとされ、仮に食品ロスを8%削減できれば、エアコンの設定温度を27度から28度に変更した場合と同等の温室効果ガス削減効果があると試算されています。このように、食品ロス削減は「もったいない」という意識から「環境への貢献」へと広がりを見せています。
食品ロスを含む食品廃棄物全体で見ると、国連の推計では2022年に世界全体で10.52億トンの食品廃棄物が発生しており、家庭・外食・小売りのいずれの分野でも3年前から増加し、全体で13%増となっています。また、国連環境計画(UNEP)の24年の報告書によれば、世界全体の食品ロス・廃棄物が温室効果ガス排出量の8~10%を占めるとされています。これは、中国(29.2%)、米国(11.2%)など国レベルの排出量に相当する規模です。
さらに生産段階に目を向けると、英国のデータサイト「Our World in Data」によれば、食品1キロあたりの生産に伴う温室効果ガス排出量(表2)では、肉類や乳製品などタンパク質食品の排出量が多くなっています。特に、牛肉や羊肉は飼料を多く要することに加え、反すう動物のゲップに含まれるメタンガスの影響で排出量が高くなります。牛は温室効果ガス全体の10.9%を排出しているとも言われており、牛1頭のゲップが排出するメタンガスは、CO2換算で自動車1.7台分に相当。食品の中で、特に環境への負荷が大きいと言えます。そのため、食品ロス削減の観点からも、肉類や乳製品の廃棄を極力減らすことが重要です。
近年、牛肉の代替として大豆由来の植物肉が注目されています。米国では、かつて代替肉の導入は健康志向が主な理由でしたが、現在では環境負荷低減を目的とする動きへと変化してきています。また、鶏肉の生産に伴う温室効果ガス排出量は牛肉の約10分の1とされており、牛肉の消費を鶏肉に切り替えることで、大きな排出量削減効果が期待できます。しかし近年、鳥インフルエンザの多発により大量の殺処分が行われ、日本や米国では卵の価格が高騰する事態になっています。鶏肉の消費を増やすには、この問題を解決する必要があります。鳥インフルエンザの遺伝子検査薬は19万2,500円と高価で、全数検査よりも安く済む全頭殺処分の方が選択される傾向にあります。この検査薬のコストが下がれば、鶏肉の安定供給が可能になるでしょう。
一方、東京商工会議所の調査によると、企業の60.1%は脱炭素に向けた取り組みを行っていないとされています。企業は取り組むべき脱炭素への施策の1つとして、全社員で食品ロスを減らすことから始めてみてはいかがでしょうか。

「中小企業家しんぶん」 2025年 3月 25日号より