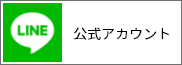下請2法(下請法と下請振興法)が今国会で改正された。規制法としての「下請代金支払遅延等防止法」が1956年の制定、「下請中小企業振興法」が1970年制定以来の大改正となる。前者が、事業者間取引の規制法であるのに対して、後者は公正取引実現に向けた振興法、支援法としての役割を果たしてきた。
半世紀以上の時を経て、今回の下請法改正は、今国会で圧倒的多数の賛成で可決成立した。今日「サプライチェーン」全体の繁栄なしには、日本経済が再生できないという強い危機感の表れでもある。
まず下請法改正の概要は次の通りである。(1)中小受託事業者からの価格協議要請への応諾義務の新設など、委託事業者の一方的な代金決定を禁止したこと(2)手形払等を禁止したこと(3)運送委託を法が対象とする取引に追加したこと(4)従業員基準を追加し、適用範囲を明確にすること(製造委託等300人、役務提供委託等100人)(5)面的執行の強化(6)「下請」等の用語の見直し(7)その他に及んでいる。
同時に改正された下請振興法の改正ポイントは、(1)多段階の事業者が連携した取組への支援(サプライチェーン)(2)国・地方公共団体の責務規定新設(全国津々浦々の価格転嫁推進)(3)主務大臣の権限強化と「勧奨」により、価格転嫁・取引適正化の実効性を高めること(4)適用対象の追加(下請法改正との連携)などである。
今回の大改正で、法律から「下請」という言葉が消える。今後は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」と「受託中小企業振興法」となり、「中小受託事業者2法」とでも略称されるかもしれない。しかし、法律から「下請」がなくなることと「下請」問題の解消とはイコールではない。
それは、衆議院・参議院での法改正に対する附帯決議(11項目)に表れている。第1項「困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小企業の立場で考えていくとの中小企業憲章の理念を踏まえ、我が国の経済活力の源泉である中小企業が、その力を最大限発揮できるよう、労務費や原材料費、エネルギーコストの価格転嫁を更に推進するため、必要な措置を検討すること」と、第2項「取引の適正化による価格転嫁から賃上げにつながる好循環が継続する社会の実現に、国民全体の理解の醸成が図られるよう、取組を進めること」は、石破内閣の賃上げと価格転嫁の好循環政策の目玉と一致している。当然、「中小企業憲章」の閣議決定から国会決議への格上げが次のステップである。
残された課題は、たくさんある。中同協の「労使見解」50年の蓄積を生かすこと、フリーランス法でも今回の下請法改正でも等閑視される中小事業に対する支援策、そして国と地方の行政機関による中小企業支援とサプライチェーン全体での公正取引の実現は、先送りできない政策課題である。
「中小企業家しんぶん」 2025年 6月 25日号より